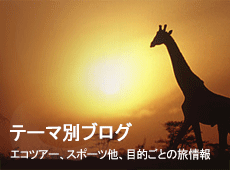今回はデジカメ
オーロラ鑑賞に行って一番知りたいのは、どうやったらキレイに自分のカメラでオーロラが撮影できるのか?ということだと思います。
カメラマンならではご意見が聞けるなんて嬉しい限り
*****
今回オーロラを撮影するために私がどんなことを準備し、どうやってオーロラを撮ったか、その一部を参考までにご紹介いたします。

(撮影2月4日:RICOH GXR A12ユニット シャッタースピード4.5秒/ISO 800/絞りF2.8)
まずはオーロラ撮影に必要なものを大きく分類すると、A)デジタルカメラ、B)三脚、C)カメラバッグとジップロック、D)手袋、この4つに分けられます。
以下順番に説明をして行きます。
A)デジタルカメラ
オーロラを撮影するためにと旅の前にカメラを新調される方も多いと聞きます。カメラを買ったら(あるいは買う前に)下記の機能がカメラに備わっていることをあらかじめ確認し、自分で設定できるように説明書を読むなりして予習をしておくと良いと思います。

(撮影に実際に使用されたRICOH GXR A12 ユニット)
私はRICOH GXRというコンパクトデジカメを使ってオーロラを撮影しましたので、このカメラで以下説明して行きます。
1)シャッタースピードが「長時間露出」に設定できること
オーロラは闇夜に広がる大変弱い光の連続です。実際に肉眼では夜空に浮かぶ霧のようにふわーっと現れては消えるといったことを繰り返すように見えてきます。それならフラッシュを使えば撮れると思われるかもしれませんが、オーロラを捉えるためには15秒~30秒という長い時間シャッターを開ける「長時間露出」という特別な撮影方法が必要です。カメラによって設定の方法は様々ですが、カメラを「マニュアルモード」にするのが一般的です。

(マニュアルモードは、カメラのダイアルの所に「M」という表示に合わせる)

(ディスプレイ左上にある「DIRECT」ボタンを押すと、カメラをマニュアルでコントロールできる画面が出てくる。黄色くなった「15S」はシャッタースピードが15秒であることを示している。左隣ははレンズの絞りで「F5.0」となっている)
2)絞りとISO感度が設定できること
暗い室内などでシャッターが適切に切れるようにするためにカメラの感度を上げるという操作を良くやりますが、これは「ISO」と呼ばれるものを設定変更することで可能になります。日中の場合ISOの数字は200が標準ですが、オーロラの場合400や800等に上げます。数字が上がることで、より多くの光をカメラに収めることができるという仕組みになっているからです。

(RICOH GXRは「DIRECT」画面ですべての設定ができるので大変便利。コマンドダイアルキーでISOを選んだ所)
気をつけなければいけないのは、感度を上げることにより出来上がりの写真に「ノイズ」といって白い細かい粒状のものが発生しやすくなり写真がザラザラした感じになりますので、ISO感度はあまり上げすぎないことがポイントです。
3)ピントを遠景に固定できること
普段の撮影の場合は「オートフォーカス」機能がありカメラが状況によりピントを合わせてくれますが、オーロラは上空数百キロで発生していますので、残念ながらカメラのオートフォーカス機能は使えません。
オーロラにピントを合わせる方法ですが、コンパクトデジカメの場合は機種によってはピントを無限大に合わせる機能がありますので、これによってピントは無限大に固定されますので便利です。

(ピントは無限大を示す∞マークに合わせてある)
一眼レフなどは無限大の機能がないのでカメラを「マニュアルフォーカス」にし、レンズを日中遠くの森の木などにピントを合わせ、念のためレンズのフォーカスリングにテープを貼って固定しておくか、月を見つけてフォーカスを合わせ同様に処理しておくと、遠くのオーロラに常にピントが合うようになります。

(一眼レフの場合はこんな風にレンズのフォーカスリングにテープを貼っておくと便利。オートフォーカスは必ずオフにしておかないと、レンズが動いてしまうことに注意)
4)予備のバッテリーを用意する
カメラを長時間外に出していると低温状態が続き、ある時間を過ぎるとバッテリーが急激に減ってしまう現象が起きます。この場合、減ったバッテリーは常温になるとパワーが戻ってきますので、バッテリーはできれば2つ持っておき、1つが減ったらポケット等にいれておいた新しいものに取り替え、冷えたバッテリーはポケットにでも入れ再度交換するようにすれば切れ目なく撮影ができます。
オーロラはその時により出現パターンは変わりますが、ゆっくりと現れる場合には30分~1時間、あるいはそれ以上の長時間上空を漂い強弱を繰り返して行きます。場合によっては突然強くなり、出現後数十秒で一気にブレイクアップといって、爆発的に全空をオーロラが覆う現象に発展する場合があります。
長く撮影しない状況が続く場合はカメラの電源をオフにしバッテリーを抜いておくなどの対策を取り、パワーを温存してオーロラの出現を待つようにするとシャッターチャンスを逃さずにすみます。

(GXRは三脚に固定するホットシューがバッテリー室を覆ってしまうので、バッテリーの取り外しに時間がかかるので注意が必要だ)
以上がカメラの機能と設定の詳細です。
現地ではオーロラビレッジのスタッフもカメラの設定等についてアドバイスをしているようでしたので、実際にわからないことがあれば尋ねてみるのも良いでしょう。ただし、それを待っている間にオーロラが出てしまった、シャッターチャンスを逃してしまったということのないように、事前に準備をしておくことが大事だと思います。
B)三脚
カメラの設定が終わったら、いよいよオーロラ撮影開始です。その際に一番気をつけなければいけないのが、カメラのブレ。シャッタースピードが15秒などという長時間になると、知らない間にカメラが動いてしまいせっかくの写真が台無しになってしまいます。これを防ぐために必要なのが三脚。撮影初日に三脚を立てて月を撮っている時に、デジタル一眼レフを持っている参加者のグループが近づいてきて「どうやったらオーロラをきれいに撮れますか?」と声をかけてきました。彼らを見るとカメラを首からぶら下げた状態でしたので、まず「三脚が必要ですよ」とアドバイス。上記のシャッタースピードの説明をした上で、以下の2つのブレのポイントについても話しました。
1)三脚はしっかりと地面に固定する
風などで三脚自体が揺れ、三脚を立てているのにカメラがブレることがあります。現場では雪上に三脚を突き刺す感じになりますので、三脚が揺れないようしっかりと地面に固定されていることを確認しましょう。またカメラが水平になっていることも要確認です。

(美しいオーロラを捉えることができたが、強風でカメラがほんの少しだけ揺れてしまった)
場合によっては天候状況により強風が吹いて三脚が揺れることもあります。撮影前には必ず三脚がしっかりと地面に固定されていること、さらにカメラが三脚にしっかりと固定されていることを確認しましょう。
2)シャッターボタンを押す瞬間に気をつける
三脚を使っていても、シャッターを押し下げた瞬間にカメラがブレが発生します。シャッターボタンは優しく押すように心がけ、場合によっては1秒などのセルフタイマーを使ってボタンが押してから時間が経ってシャッターが切れるように工夫しても良いでしょう。私は「シャッターレリーズ・ケーブル」というケーブル式のシャッターボタンをあらかじめ用意してカメラに取り付けておきました。
以上が三脚についてです。
スーツケースに三脚が入らない等の理由で現地に三脚を持って行けない時にはビレッジでレンタルすることができるようですので、そういったサービスを利用しても良いでしょう。
C)カメラバッグとジップロック
外気温はマイナス20度を越える低温のため、ティーピーや休憩所には暖房が入っています。私たちにはありがたいサービスなのですが、カメラとレンズにとってはこの温度差が大敵です。
寒い所から急に暖かい部屋に入ると眼鏡が曇るのと一緒で、カメラのレンズもあっという間に曇ってしまいます。問題なのは見えている外側のレンズだけではなく内側(通常レンズは何枚ものレンズが組み合わさってできている)も曇ってしまうと、大変ややこしいことになります。
現地にいる間、スープを飲みに休憩所に入ってくる人の中には三脚にカメラを取り付けた状態のままの方がいたり、同様の状態でティーピーに入り暖を取る方を多く見かけました。見ていると、指でグリグリとレンズを拭いてスープを写真に収めている方、カメラに布を巻いている方、あるいはまったくカメラを放ったらかしにしている方など様々でした。こうしたカメラの扱いについてはおすすめできません。
デジタルカメラは電子機器なので急激な温度差には弱く、扱いを間違えると場合によってはカメラが壊れてしまうこともありますので、下記を参照にぜひ大切に扱っていただきたいものです。
1)ある程度密閉できるカメラバッグに入れる
ジッパーがついたカメラバッグにカメラを収めることで、急に暖かい空気がカメラに触れることを防ぐことができます。

(私のカメラバッグは内側が厚く温度変化に強いタイプになっていた)
2)ジップロックなど密閉できるプラスチックバッグにカメラを入れる
上記と同様の理由でカメラを外気に直接触れさせないために、冷凍庫で使える市販のお料理用プラスチックバッグ(しっかり密閉できるもの)にカメラ(場合によっては本体とレンズを別々に)をしまい、しっかりと口を閉めてカメラバッグにしまいます。

(カメラはこのようにジップロックに入れ、しっかり蓋をして外気が入り込まないようにする)
実際、三日目の撮影の折りに外気温はマイナス20度、体感温度26度の状態で1時間以上外にいたために体調が悪くなってきたので、カメラを上記のような状態にしてしまい、休憩所に入った後は暖房から遠い所(壁際)にカメラバッグを置き、暖を取り、暖まったら1時間ほどしてまた現場に戻るということを2度繰り返しましたが、カメラとレンズは常に低温のままで、機能にも異常がなく撮影を続けることができました。結論的には、上記の手当をしてカメラとレンズが急激な温度差にさらされないようにしておけば、必要以上に神経質になる必要はないと感じています。

(しっかりジッパーを閉じると、それだけでも保温効果が出る。撮影が終わり部屋に帰ったら、この状態で朝までカメラはさわらない)
私が持って行ったカメラバッグはかなり厚手の本格的なものでしたので、薄手の生地のカメラバッグの場合にはジップロックの外側からタオルで巻いておく、などの手当が必要かもしれません。
以上がカメラの冷温対策です。
D)手袋
防寒用の手袋はご覧の通り厚手のもので、指が出ないタイプのものです。バッテリーを交換したり、カメラの設定を変更したりする必要を考えて、利き手は指が使えるタイプの手袋を用意してください。

(ツアーでレンタルした防寒具。この手袋ではシャッターを切るのは無理)
特に三脚は凍り付いている可能性が高く、金属部には絶対素手で触れたり、偶然であっても他人に触れさせてはいけません。万が一触れてしまった場合(とくに指が張り付いてしまった場合)はケガの可能性が高くなりますのでまずはあわてず、何もせずにすぐスタッフに声をかけて応急処置の方法を尋ねてください。

(手袋は二枚重ねにした)
こういった事態を防ぐためにも、どのような場合でも常に手袋は着用していなければなりません。
もう一つ、万が一薄手の手袋を使う場合、長時間低温状態に置いていると凍傷になる危険性がありますから十分に気をつけてください。
私が現地で一番効果的だと感じたたのは「指先が痛くなったらすぐに脇の下に入れる」という方法です。「痛くなる」のは通常のことですのであわてる必要はありません。大事なことは痛いと感じた時に「すぐ」温めることです。

(イエローナイフは日中でもマイナス20度を超える)
カメラとは関係のない話題ですが、まれにオーロラを見て興奮するあまり上着を脱ぎ捨てて走り回る若者がいる、という噂を聞きました。怪我や事故はほんのちょっとした「心の隙(すき)」から起こるものです。旅先で感動し、特にグループで行動している場合には周りに友人がいることで気分が弛み、状況が分からなくなってしまうことも起きやすいようです。その場合は、グループ内で周りのことも考え、お互い注意し合うことこそ本当の友人関係ではないかと思うものです。
特に三脚などの機材を持っている場合には周囲に対して注意深い行動が必要になりますので、そのことは最後に付け加えて皆さんにもお伝えしたいと思います。
以上、うるさいことを最後に書いてしまいましたが、それでも自分の目で見たオーロラが記憶の中だけでなく自分が撮った写真として残せるということは、生涯の思い出になるものです。ぜひ皆さんも手持ちのデジタルカメラを使い、「自分の目で見たオーロラ写真」を旅の想い出に持ち帰っていただけるよう心から願うものです。

(撮影2月3日:RICOH GXR A12ユニット シャッタースピード8秒/ISO 800/絞りF2.8)
最後にもう一つ、オーロラの出現のタイミングはビレッジのスタッフさんが教えてくれます。3日目のことですが、はやる気持ちを抑えきれずに到着直後から丘に上がってオーロラを待っていたのですが、途中でマイナス20度越えの寒さに耐えきれずにティーピー(昔ながらの三角テント)に戻るという失敗をしてしまいました。結局この日は到着してから3時間経ってオーロラが出現、その後にブレイクアップを目撃しました。
ビレッジのスタッフさんは常に空を監視していて、ほんのわずかな変化も見逃さずに私たちに伝えてくれますので、その点は安心して良いのではないかと思います。最終日は何と移動のバスの中からオーロラが出ていたのですが、その後静かになったのでティーピーでホットチョコレートを飲みながら次のオーロラの出現を待ちました。これまで飲んだどんなものよりも美味しかったホットチョコレート、ぜひオーロラ鑑賞の合間に試してみてくださいね!

(撮影2月4日:Nikon D3S シャッタースピード20秒/ISO 2000/絞りF6.3)
-
投稿: 来栖 -2012年11月13日 (火) 15時21分
■無題
初めてお便りします。来年1月にフェアバンクスのノースロッジにオーロラを観に行きますので、ブログの内容が大変参考になりました。そこで、内容に関しての質問です。このたび、ファームアップによりGXRのS10ユニットに、バルブ機能が加わりました。ワイドコンバージョンレンズを使用すると、28mmよりは広角に撮影できると思いますが、センサーの差は撮像に影響するとも思います。この条件で、両者を比べると、現場でどちらを選ぶのが正解でしょうか? -
投稿: 来栖 -2012年11月14日 (水) 01時51分
■補足です。
さきほど質問をしたものですが、言葉足らずのところがありましたので、補足させていただきます。「この条件で、両者を比べると、現場でどちらを選ぶのが正解でしょうか?」この両者とはA12とS10+DW-6(センサーが小さい)を指します。すみません、お答えいただければ幸いです。 -
投稿: MAKOTO -2012年11月28日 (水) 18時01分
■MAKOTOです
日本出張でお返事が遅くなりすみませんでした。お尋ねの件ですが、経験的に言うとA12ユニットの方が寒さには強いと思います。もちろん、メーカーが保証する温度より、イエローナイフの冬の気温はかなり下がりますから、ユニットを長時間冷温にさらさないように気遣いが必要かと思います。実はこのときS10を持って行ったのですが、撮影はできませんでした。たぶんユニット自体が寒さに対応できなかったのかもしれません。この時は夜間でマイナス20度ほどでした。 -
投稿: だめ人間 -2012年12月11日 (火) 04時45分
■質問させてください。
はじめまして。だめ人間と申します。年末にアイスランドへオーロラを観に行くのですが、その際にGXRのP10ユニットでの撮影を考えております。当方、カメラに疎いものでこちらの内容を参考にさせていただこうと思ったのですが、P10よりA12ユニットの方がオーロラの撮影には適しているのでしょうか?お手数ですが、お答えいただければ幸いです。よろしくお願い致します。



 テーマ: 観光
テーマ: 観光