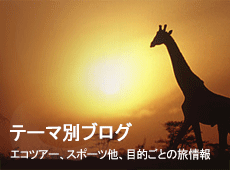昔の習慣では、農暦の12月23日から、正月の15日までは
「大年(新年を迎える期間)」とされていますが、本当の「新年」は、
大晦日の日から新春の初五(農暦正月五日)までで、この五日間は、
「火」を点けず、「鋏み」に触れず、「包丁」にも触らない生活をします。

伝説によると、火をつけて料理を作ると「火事の災」にあい、鋏みを使う
と「口喧嘩の災」にあい、針で裁縫をすると「目の災」にあい、包丁を
使うと「出血の災」にあい、又、ゴミを捨てずに「宝を貯める」とされていま
すが、一年間苦労してきた家庭の主婦を休ませるという意味もあります。
「破五」の意味は、この日を過ぎればすべての禁固が解禁されて、
本当に新しい春を迎え、新しい年が始まるとの意味です。![]()
この日を迎える為、北方の多くの家庭では餃子を作り、又わざわざ
何個かを破って「破五」を迎えるのです。![]()
「初五」の日は新春の始まりだけでなく、
「財神(財産を配る神)」の誕生日とも言われています。 ![]()
黄(キイロイ) ではまた~



 テーマ: 民俗風習
テーマ: 民俗風習