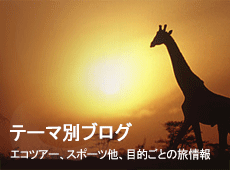ヴェネト州には城壁に囲まれた小さな町が点在します。
その中でも最も美しい壁の町として有名なのが、モンタニャーナMontagnana。
フェッラーラ領主エステ家が1275年まで、その後はパドヴァ領主となるエッツェリーノが町を治めていた歴史があります。
その頃には、ここでも後述する壁の、随一の門ともなるカステッロが建設されています。これはヴェローナを治めるスカーラからの防御を目的としたものでしたが1317~1337年の間はヴェローナがここを占拠していたとされています。それ以降、再度パドヴァの手に戻り、パドヴァ領主エッツェリーノ・ダ・ロマーノ、そしてカッラーレージ家による統治を経て、1405年以降はヴェネツィア共和国下の傘下となりました。長い歴史です。
2kmにも及ぶ、この町のシンボルであり、地元民の誇りでもあるのが現存するアンティークな壁です。
東西に長い長方形をした壁の周囲は、今は草地となっています。
本来は掘とスパルトspaltoと呼ばれる中世ルネサンス期の城の防御用の峡間を備えた斜堤が張り巡らされていて、完全に外部の敵からの防御のために建築されたものです。
壁の要所には高さが17-19メートルにもなる24の塔がほぼ定間隔で建っています。また外部との行き来のために設けられた主要な門は東西に2箇所あります。(現在は鉄道駅から旧市街へ入る門も設けられています。)
東側の門はレニャーノ及びマントヴァ方向に、西側のものははモンセリーチェ及びパドヴァ方向に向いています。
特に位置的にも重要視されていたのが、パドヴァ側にあるカステッロ・ディ・サンゼロcastello di S.Zero。1242年にパドヴァ領主のエッツェリーノ・ダ・ロマーノにより築かれました。
建物の一部はヴェネツィア共和国時代には、建物の一部はヴェネツィア商人の東方貿易により運ばれた麻繊維の保管場所とされ、またその後ナポレオンの時代には、兵士たちの宿舎として使われていました。
現在は、市立博物館となっています。
博物館は2.1ユーロでガイドつきで内部を見学することが可能。紀元前期、古代ローマ時代~中世へと、ここで出土した当時の貨幣(古代は貝殻)や食器、墓やその中に収められていた埋蔵品などが展示されています。1300年代の建物の内部に入ることができるうえ、丁寧な解説で大変に興味深いのでお勧めです。内部はそれほど大きくないので、短時間で回れて、何よりも良心的な価格です。
それに対し、東側の門は1300年代建築のロッカ・デッリ・アルベリrocca degli alberi。現在、建物の一部は簡単な宿泊施設となっているようです。
壁に囲まれた市内に入ると旧市街は他の町と同様、ドゥオーモとその前面に広がる広場(ピアッツァ・ヴィットーリオ・エマヌエレ2世Piazza Vittorio EmanueleⅡ)を中心に構成されています。
毎年9月第1週の日曜日に11のコムネ(周辺の地区)間で行われるパリオ(競馬レース)は伝統的な行事で毎年イタリア各地から多くの観光客が訪れます。
その他、毎月第三日曜日のアンティーク市、10月の食品展覧会など、小さいながらに魅力の多い場所。
そして、ここを訪れて忘れずに味わっていただきたいのが、1996年にDOPに指定されているプロシュット・モンタニャーナ。正式な名はプロシュット・ヴェネト・ベリコ/エウガネオProsciutto Veneto Berico-Euganeo。「ベリコ」と「エウガネオ」とはモンタニャーナの町の背景にある丘陵地帯を指します。
プロシュットはまさに自然の産物。
その製造方法は簡単にいえば、塩漬け後乾燥することにつきます。
その過程の要所要所で熟練の職人の目や感覚が重要なキーポイントとなり、その土地の空気を素材にして仕上げるもの。
環境もそして製造方法も概して原始的ですが、この地の空気でしか生まれることのない産物なのです。
モンタニャーニャ産のプロシュットはパルマのそれほど有名ではなく、また生産量も少ないので、通常ヴェネト周辺で、そして外国へはドイツの一部に卸すのみといわれています。
もちろん日本への輸入は解禁されていませんので、希少価値のある旨いプロシュットです。
キリリと冷えたプロセッコに合わせるとさらにおいしいそうです。
毎年5月にはプロシュット祭りも開催されており、今年は5月15から17日の3日間でした。

●モンタニャーナへのアクセス方法●
ヴェネツィアからマントヴァ行きの直通電車、
またはボローニャ行きに乗り、モンセーリチェで乗り換えて行くことができます。
記事&写真提供:特派員白浜さん



 テーマ: 特派員記事
テーマ: 特派員記事