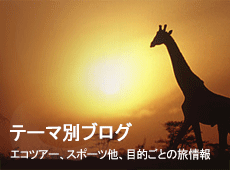今回はアルベロベッロを少し離れ、最近私が訪れたプーリアの町「バルレッタ」をご紹介。 ●町の印象●
●町の印象●
穏やかな気候に恵まれた海沿いの町バルレッタは、バーリから海岸線を北上して約60kmの所にある人口約93000人の町です。
自然、歴史、文化、芸術、考古学、そして食文化の中心となるワイングルメなど、様々な側面で独自の魅力を持っています。
活気に満ち溢れた町は、「歴史ある町並」に新しい息吹を与え、過去から続いている歴史の「今」をしっかりと描き続けている感じを受けます。
旧市街の町並は、私が好きな石畳と細い路地が多く、セピア色が似合うトスカーナ地方の小さな町を思わせます。
私がこの町を訪れたのは日曜日だったのですが、午前中の人ごみ、午後の静けさ、夜の賑わいと時間帯で変化する町の「顔」が非常に印象的でした。
午前中は、家族連れや、若者グループが目立ち、とにかく人の往来が多い、騒がしい町でした。
また、お城の敷地内の緑地は恰好の憩いの場を提供していて、走り回る子供達、それを見守る両親、のんびり散歩する老夫婦、声高に話しまくる若者のグループ、ベンチのカップル、ペットを散歩させる人、音楽をかけて踊る人達などなど、全ての年齢層の男女が、健康的な休日を楽しんでいる印象を受けました。
ところが午後1時を過ぎると町は一変、人っ子一人いない空虚な町に早変わり、商店は全てシャッターを下ろし、僅かにバールが数件開いているだけです。人で溢れかえっていたお城の敷地内も緑の芝生だけが目立つ静かな空間になってしまいました。
そして夜、日が傾き、辺りが薄暗くなると、レストランや、バール、スナックなど、お酒を楽しむ大人向けの店に灯が点り、町に再び人が溢れ出し、賑わいが戻ってきます。午後の静けさが嘘のように、どこからともなく溢れてきた人波は家族連れよりカップルが目立ち、町はお洒落なネオンで彩られます。
●町の歴史●
町の歴史は紀元前4-5世紀に遡りますが、バルレッタが誇る豪華で輝かしい歴史は、中世期以降に始まります。ノルマンディーの要塞として栄えた町は、聖地パレスチナへの出航に都合のいい場所に位置する事から、アドリア海沿岸の重要な港の1つとなり、十字軍のパレスチナ遠征の出発拠点をはじめ、商人、巡礼者、戦士など、聖地へ向かう人々の通過点として位置づけられました。人の往来の増加に伴い、商業が発展し、経済的にも豊になっていきました。
 ●カステッロ●
●カステッロ●
海に面して堂々たる姿を見せるカステッロ(お城)は、「16世紀に皇帝カール5世が建てた」と言う説と、「12世紀から16世紀に亘り、4者(ノルマンディー、ホーエンシュタウフェン朝、アンジュー王朝、スペイン王朝)の手によって建築された」と言う説の2つがありますが、完成期が16世紀と言う事は、どちらの説にも共通しています。
「お城」と呼んではいるものの、実際は要塞として使われていたようで、「岩の塊」の様な風貌をしています。バーリやモノーポリにも、似たようなお城が海に面して建っています。
かつて国の情勢が不安定だった時代、海沿いの町は、海からの侵入者を防ぐため、頑丈な城壁を持ったお城の建築を余儀なくされました。そのほとんどは、攻撃より守備に重点を置いた作りになっています。
折角なので、入場見学しましたが、お城としての機能を果たした内部部分はあまり見学する所はなく、唯一、フェルディナンド2世の胸像に興味を惹かれただけでした。
ところが、余り期待をせずに「進路」に従って入って行った地下部分は広くて、かなりの見応えがありました。食糧や武器の保存に使われていたという内部は、土がむき出しのままになっていて、いくつものドームや小部屋に別れています。大きいドームに足を踏み入れると、靴音が土を踏んでいる足元ではなく、ドーム全体から響いてきて、何だか妙な気分でした。ドームの一つは、内装を施し、現在コンベンションセンターとして使われています。
小船に乗ったまま城から海へ出るための鉄格子の扉は、映画「仮面の男」(だったかな?)でレオナルド・デカプリオ演じる王の、双子の弟が囚われていた牢屋の入口を思わせます。カステッロの屋上からは、新市街の町並や海が見渡せました。
●決闘の町●
歴史上に残る「バルレッタの決闘」は、イタリア国内はもちろん、海外にも広く知られています。16世紀初頭、ナポリ王国の領土分割を巡り、スペインとフランスは激しい戦いをしていました。ある晩、スペインの占領下にあったバルレッタの地下の酒場で、スペイン軍が晩餐会を開きました。この宴には、スペイン軍に属し、勝利に貢献する勇敢な戦いをしたイタリア騎士団のほか、フランス人捕虜も招かれていました。捕虜を招いて宴会をするあたりが、いかにもイタリアっぽくていい感じですが、その宴会の最中、捕虜の一人がイタリア人に浴びせた辛辣な言葉が、バルレッタ出身の騎士エットーレ・フィエラモスカを侮辱した事から、対立が起こり、後日の決闘へと発展しました。
もし、日本だったら「無礼講」という言葉で丸く納めたところだったのでしょうが、ここではそうはいかなかったようです。1503年2月13日の朝、13人のイタリア騎士団は、町から10kmあまり離れた教会のミサで、決闘に勝つか死ぬかを誓い、その足で決闘の地に赴きました。そして、13人のフランス騎士団と一戦を交え、見事勝利を納めました。バルレッタには、この決闘のきっかけとなった地下の酒場が今も残り、見学する事が出来ます。
 ●カテドラル●
●カテドラル●
カステッロの向いあるカテドラルはバルレッタで最も古い教会で、より古い前面部分はロマネスク様式で、1147年に建てられたました。その後、ゴシック様式で建てられた後ろの部分は、43mの高さを誇る鐘楼から建築が始まり、鐘楼の台座には、1503年の決闘の勝利を讃えた「偉大なる勝利」、1528年に起きたフランス軍や内部の徒党による略奪の記憶を示す「町の破滅」の文字が刻まれています。
1459年2月4日、当時南イタリアをほぼ手中に収めていたアラゴン王朝のフェルディナンド1世がこの教会を訪れた事が、貴重な歴史の1ページとなっています。
 ●ヘラクレイオスの巨像●
●ヘラクレイオスの巨像●
町中でひと際目を惹くのが、サントセポルクロ教会の前に立っている、高さ約5mのブロンズ像です。一般的には東ローマ帝国の皇帝ヘラクレイオスの像と言われていますが、テオドシウス2世だとの見解もあります。1309年からその存在は確認されていますが、最も古い仮説としては、6世紀に製作された可能性もあるそうです。
像は40歳の皇帝が帝国で最高の栄誉を手にした瞬間を表現し、鎧に身を固め、左手の掌中に世界征服の象徴である球体を載せ、右手は十字架を高く掲げています。
 ●画家ジュゼッペ・デ・ニッティス●
●画家ジュゼッペ・デ・ニッティス●
1846年この地で生まれ芸術家としての人生の大半をパリで過ごしたデ・ニッティスは、今も尚、この町を語るのに欠かせない人物です。
ヨーロッパで名を馳せたデ・ニッティスの影響は、この町が芸術面において力を注いでいることに強く表れています。
ストリートギャラリーで新進画家の発掘をしたり、絵画だけに留まらず、音楽の分野でも様々なコンクールを開催しています。
現在、デ・ニッティスの作品「ナポリの婦人」が、絵画美術館と同じ建物の中に展示されています。この絵は、バルレッタの町が買取ったもので、45万ユーロの代物だそうです。
バルレッタの町は如何でしたか?
この町は既にアンドリア、トラーニと合併し県に昇格する事が決まっています。
2008年から実質的な県庁所在地として、新たな歴史を刻んでいく事でしょう。
交通:
バーリから国鉄バルレッタ駅下車又は、バーリから私鉄Nordbarese線
アルベロベッロは、雲のない日は特に放射冷却現象によって冷え込みが厳しくなっています。
旅行を予定している皆さん、南だからと言って軽装は禁物です。秋の装いではなく、冬支度で来て下さい。
記事・写真提供:特派員野口さん



 テーマ: 特派員記事
テーマ: 特派員記事